Welcome to Hoistoredio. This is for English and History Learners by an English and History Learner.
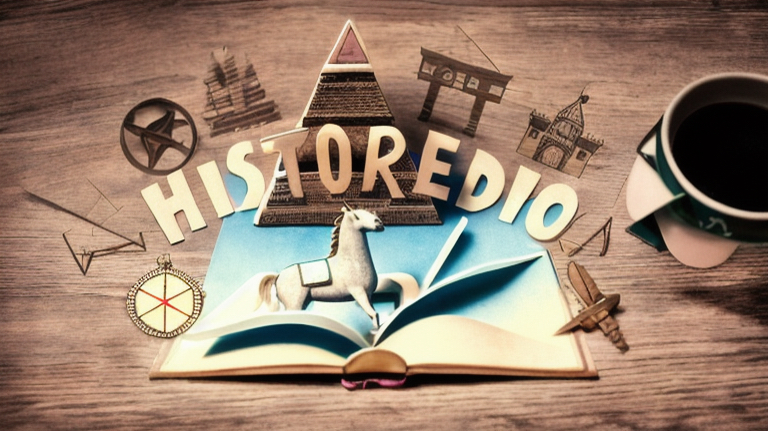
Historedioについて、このウェブサイトはpodcast【Historedio】のためのものです。ヒストレディオはどんなものなのか、何故作り始めたのか、何度か書こうとしたけれど、その度に胸が一杯になってしまい、このページをアップデートできずにいました。
3話目の配信が終わり、少しづつ形が見えてきたので書いてみることにします。
Historedioは英語と世界史が一緒に学べるpodcastで、世界史と英語の学習者である日本人のおばさんが制作しています。難易度としては世界史は超入門、英語は英検準一級相当かと思います。なおタイトルはラジオが大好きなのでhistoradioとしたかったのですが、これだと「ラジオの歴史」という意味が強く、「グリエルモ・マルコーニ(※イタリアの発明家)が〜」とか「 バグルスのあの曲は〜(※Video Killed the Radio Startという曲を発表)」といったラジオ史を題材にしたコンテンツと混同されてしまうため、historedioという固有名詞にしました。
私は中学校と高校の学校での勉強が嫌いでした。正確に言うと大好きなものとつまらないもの(そして拒否して完全に勉強しなかった)の2つに分かれました。大好きな科目は音楽、生物、化学、数学。嫌いで勉強しなかったのはそれ以外全部です!英語もほぼ勉強していませんでした、「ルールが理解できないし一生使わない予定」という理由で。社会科は最初の1ヶ月くらいは楽しく授業を受けていましたが、好奇心旺盛な私は疑問が大量に湧いてしまい、ただひたすら暗記していく詰め込み式の学校の授業についていけなくなってしまいました。また何故か地理の先生がしがちな「自分はここに行ったことがあるよ!」エピソードが自慢にしか感じられずイライラもしました(大人になった今なら自分が身をもって経験したことの重要さが理解できますが)。理屈がわからないものを学ぶことがどうしてもできなかったのです。
高校を出て好きな分野に進み、どうしても英語が必要になり必死に英会話を勉強しました。それから英語や異文化の面白さを知り、ぐんぐんとリーディング以外の英語力を伸ばすことができました。その一方で「英語教育ビジネス」に疑問を感じました。大量の書籍、レッスン、情報…。ある程度のレベルまでの外国語習得はそれほど難しいものではないと思うのですが、学習者が簡単に英語を習得してしまえばこうした商売は成り立ちません。そう、巷にあるものの殆どは英語が使えるようにならない勉強方法です。英語研究者でない限り、英語を勉強するよりも、なにか別の目的を達成するための言語ツールとして英語を勉強するほうが習得は速くて正しいと私は信じています。そんな訳で【英語で何かをする】という勉強方法が私は大好きです。
社会に出てから様々な人に出会いました。中にはとても素敵な考えをお持ちの方がおられ、そうしたひとの多くは歴史に精通していました。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という名言があるそうですが、自分が経験したことから学ぶには限りがあり、過去の歴史からは非常に多くのことが学べる事に気づかされます。10年ほど前に自分で歴史についての本を読んだり、友人に教えてもらいましたが、どうにもつまらない…1,2年前にも「COTENRADIO」という人気podcastを教えてもらいました。確かにとても面白いのですが、情報量がとても多く、歴史経験がゼロどころか苦手意識のある「歴史経験値・マイナス状態」の私には難しすぎました。(補足しておきますがCOTENRADIOはとても面白いです)。それから気づいたのですが歴史に詳しい人がする歴史の説明には歴史用語が含まれているため、説明されても意味がわからないのです。日本語で説明してもらっているのに理解できない…自分の自尊心が削られて、歴史を勉強しようとすればするほど、学習するモチベーションがどんどん下がっていきました。
一方で英語は知らない単語が出てきても、お、新しい単語が出てきた、学習のチャンス!と素直に受けいられるので、ひょっとして英語で世界史を勉強すれば良いのでは?というアイディアを思いつきました。苦手なリーディングも克服できそうですし、英検準1級は知らない情報についてのリーディング問題が多いので英検対策にもなりそうです。
例えば「封建制度」を日本語で調べてみると、
封建制度 天子・皇帝・国王などの直轄領以外の土地を、諸侯に分割領有させ、諸侯はそれをさらに臣下に分与してそれぞれ自領内の政治の実権を握る国家組織。
https://ja.wikipedia.org/wiki/封建制 より
えっと、天子ってなに?諸侯って何?分割領有というのもなんとなく分かるような分からないような…と日本語なのに意味が分からなくて落ち込みます…
英語の辞書で封建制度にあたるfuedalusmを見てみると
the dominant social system in medieval Europe, in which the nobility held lands from the Crown in exchange for military service, and vassals were in turn tenants of the nobles, while the peasants (villeins or serfs) were obliged to live on their lord’s land and give him homage, labor, and a share of the produce, notionally in exchange for military protection.
New Oxford American Dictionary より
難しめの単語があるけど英語のほうが分かりやすい!
そして同じ用語でも、日本語で調べるとまずは日本史における文脈で語られるし、英語だと最初に来るのはアメリカやヨーロッパの封建制度について。英語の場合は「様々な文化で封建制度があり…」と前置きが入ったりもします。
そうして日本語で学ぶ世界史と、英語で学ぶ世界史には差があること、最新情報のタイムラグが有ることにも気づきました。例えば中学校に入り最初に習った(ハズ)「世界四大文明(メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、中国文明)」は英語でなんて言うのか調べてみたところ、直訳が存在しないことに驚きました。4つの有名な文明が発展していた横でその他にもいくつも文明があったのです。そこで英語では「四大文明」+その他の文明= cradle of civilization (文明のゆりかご)と呼ぶということに気づきました。私はとても驚いたので事実確認をしなければ!と、カナダ人とアメリカ人のネイティブにこの話をしてみたことろ「四大文明?!ありえないね、なんでそんな言い方するの?他の文明はカウントされないの?」と2人も非常に驚いていました。世界四大文明なのに世界共通の考え方ではなかったのです。英語で世界史を学ぶことで海外の視点も学ぶことができます。
そこから英語で歴史についての記事をリーディングし始めるのですが、一人では心が折れてしまいます。私が三日坊主にならない方法 – それは仲間を作ることです。音声SNS「Clubhouse」には平日の毎朝30分ほど英語の記事を一緒に読んでくれる仲間がいたので、たまに世界史の記事を一緒に読んでもらうことにしました。よく一緒に助けてくれるメンバーが4人おり、3人は私と同じく日本人で英語学習者です。英語や語源に関する知識が豊富なJさん、知的な感想をいってくれるNさん、理系よりのコメントをくれるIさん、そしてプロの英語発音Cさん。特にCさんには単語についてのトリビアや固有名詞の発音についてのアドバイスを頂き感謝しきれません。
つづく